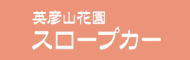ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
梵鐘(ぼんしょう)
| 指定種別 | 県・有形文化財(工芸品) |
|---|---|
| 指定年月日 | 昭和41(1966)年10月1日 |
| 製作年・時代 | 文禄3(1594)年 |
| 員数 | 1口 |
| 構造等 | 総高122.8m、撞座径10.5cm、口径72.4cm、縁厚8.6cm |
| 所在地 | 添田町大字英彦山 英彦山神宮境内 |
| 備考 |
英彦山神宮境内の鐘楼にかかっている鋳銅製の梵鐘で、毎年12月31日には、除夜の鐘としてこの梵鐘をつくことができます。
南北朝時代に制作された肥前鐘で、文録3(1594)年、岩石城主の毛利久八郎が般若窟より移設して寄進したものです。「梵鐘文禄三年追銘」との記載を読むことができます。
英彦山に現存する梵鐘は1口だけですが、行橋市今井の浄喜寺の梵鐘に「彦山霊山寺大講堂洪鐘―以下略―」の銘文があり、かつて彦山大講堂前庭にも鐘楼にあったことが分かっています。
※「般若窟」…彦山四十九窟の第一窟。現在は、玉屋神社。
古代彦山の修行は窟に籠る「窟籠修行」であったと考えられ、英彦山の由緒や縁起を記した『彦山流記』には、四十九の窟名が挙げられています。