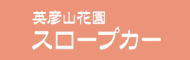ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
修験板笈(しゅげんいたおい)
| 指定種別 | 国・重要文化財(工芸品) |
|---|---|
| 指定年月日 | 昭和34(1959)年6月27日 |
| 製作年・時代 | 元亀3(1572)年 |
| 員数 | 1背 |
| 構造等 |
総高115cm、背板高70cm、背板幅50.5cm、足長50cm、壇板縦53.8cm、横33.7cm |
| 所在地 | 九州国立博物館保管 |
| 備考 |
壇板の板金に、大檀那座主舜有以下二十七修験者名と「元亀三天壬申閏正月十八日細工人津村太郎次郎」の刻銘 |
元亀3(1572)年に寄進された、現存する中で最古の板笈です。
藤の一木を折り曲げた枠の上半部に板を張り、背面には二羽の鷹と阿吽の獅子がそれぞれ金銅で打ち出された、非常に荘厳な笈です。
壇板の銘板に名の書かれた「座主舜有」は、座主が山内ではなく、英彦山南西の黒川(現:朝倉市黒川地区)に居を構えていた時代(1333~1587)の最後の座主です。
現在は、九州国立博物館で保管されています。
※「笈(おい)」…修験者が仏具や衣類、食器など修行に必要なものを入れて背負う道具のこと。