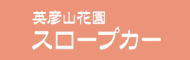ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
英彦山神宮奉幣殿(ひこさんじんぐうほうへいでん)
| 指定種別 | 国・重要文化財(建造物) |
|---|---|
| 指定年月日 | 明治40年5月27日 |
| 製作年・時代 | 元和2年(1616) |
| 員数 | 1棟 |
| 構造等 | 桁行七間(22.38m)、梁間五間(16.9m)、入母屋造、向拝一間、こけら葺 |
| 所在地 | 添田町大字英彦山 英彦山神宮 |
| 備考 | 英彦山神社」は、昭和50(1975)年6月24日に「英彦山神宮」に改称されました |
山内最大の建物であり、かつては霊仙寺の大講堂で、英彦山修験の中心的構造物でした。
現在の社殿は、元和2(1616)年に小倉藩主細川忠興によって再建されたもので、当初は寄棟造でしたが、享保8(1723)年に小倉藩主小笠原忠雄により、大屋根の入母屋造に改造されています。
再建時の建立棟札をはじめ、寛文5(1665)年、享保8(1723)年、宝暦13(1763)年、嘉永6(1853)年の修復の際の棟札が伝存しています。
『彦山流記(ひこさんるき)』に「大講堂一宇 二階 七間」とある前身建物は、永禄11(1568)年の豊前大友氏の焼き討ちにより焼失しました。平成18(2006)年の修理工事の際、前身建物の礎石が発掘され、遺物等から、前身建物の建立は平安末から鎌倉初期頃であることが分かっています。