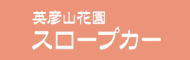ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
英彦山神宮銅鳥居(ひこさんじんぐうかねのとりい)
| 指定種別 | 国・重要文化財(建造物) |
|---|---|
| 指定年月日 | 昭和14年10月25日 |
| 製作年・時代 | 寛永14年(1637) |
| 員数 | 1基 |
| 構造等 | 青銅製明神鳥居 |
| 所在地 | 添田町大字英彦山 英彦山神宮参道 |
| 備考 | 「英彦山神社」は、昭和50(1975)年6月24日に「英彦山神宮」に改称されました |
寛永14(1637)年、佐賀藩主の鍋島勝茂の寄進により建てられたもので、高さ7m、柱の周囲は3m余りもある胴の太い青銅製の鳥居で、柱は青銅製の円筒6個を積み重ねてできています。
『英彦山』の扁額は、享保19(1734)年に霊元法皇の勅命を受けて京都から運ばれて架けられたものですが、それ以前にどのような扁額が架けられていたかは分かっていません。
また、この鳥居は、かつて彦山町の付近にあり、貞享3(1686)年頃に現在地に移されたといわれ、その際、柱輪各1個をはずしたため総高が低くなり、全体的にずんぐりした形になったと言われています。
※英彦山は、天照大御神(日の神)の御子神である正勝吾勝勝速日天忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)が鎮座する山として、「日子山(ひこさん)」と呼ばれていました。その後、弘仁10(819)年に嵯峨天皇の詔勅により「日子」の2文字が「彦」に改められ、享保14(1729)年には、霊元法皇の院宣により「英」の1文字を賜り「英彦山」となりました。