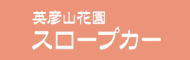ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
英彦山(ひこさん)
| 指定種別 | 国・史跡 |
|---|---|
| 指定年月日 | 平成29(2017)年2月9日 |
| 製作年・時代 | ― |
| 員数 | ― |
| 構造等 | ― |
| 所在地 | 添田町大字英彦山 |
| 備考 | ― |
英彦山は、平成28(2016)年11月18日に国の文化審議会で史跡指定の答申がなされ、平成29(2017)年2月9日付け官報で告示され指定されました。
(以下、文化庁「史跡等の指定等」史跡等の指定等について<外部リンク>p.5より抜粋)
標高約1200mの南岳・北岳・中岳の3峰から成る信仰の山である。山頂には経塚が多数営まれ、山中行場として玉屋般若窟に代表される修行窟が整備された。神仏が習合して彦山権現が誕生し、それを讃える祭礼が整えられると、院坊が智室谷をはじめ各谷に配された。さらに、大講堂を本堂とした伽藍が整備され、彦山霊仙寺としての寺格が確立する。
室町時代には熊野修験の影響を受け、金剛界竈門山(宝満山)、胎蔵界彦山を往来する峰入行が開始された。戦国動乱期にほとんどの建物が焼失するが、江戸時代に入ると、小倉藩主細川忠興をはじめ諸大名から寄進を受けて再興を遂げ、享保14年(1729)、霊元法皇より「英彦山」の勅額が下賜された。明治元年(1868)の神仏分離令により、英彦山霊仙寺は英彦山神社(現在の神宮)となり今日に至っている。
英彦山霊仙寺(英彦山神宮)の境内域から銅鳥居までの約1kmの大門筋の両側には多くの坊舎が並び、座主院跡には石垣や礎石が極めて良好に遺存している。中岳山頂に上宮社殿が建ち、山頂に至る参道も良好に維持されている。また、神社に姿を変えた修行窟も現在まで英彦山信仰の中核をなしている。
このように、英彦山は、我が国を代表する山岳信仰の遺跡で、我が国の修験・仏教・神道の信仰の在り方を考える上で重要である。