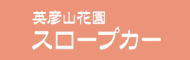ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
岩石城(がんじゃくじょう)跡(1)
岩石山(がんじゃくさん)

岩石城は、保元2(1157)年、平清盛がその臣、大庭景親に命じて築かせたということです。その後たびたび戦いがありましたが、豊臣秀吉の九州平定のときの戦いがもっとも激戦だったでしょう。徳川幕府による元和元(1615)年の一国一城令によってこわされましたが、遺構がたくさん残されています。
添田公園と「ふれあいの館」の前の舗装道路を約700メートルばかり登ると、右側に「鷲越峠経由登山口」の案内板があり、この道を登れば50分で白山宮奥の宮(8号目)につきます。
もう一つの登山道は、さらに舗装道路を進みます。約500メートルで左側に「頂上登山口」の案内板があり、山道に入り約800メートルで石の祠のある白山宮奥の宮につきます。
ここはいま、登山者のための休憩所ができていますが、地形をよく見ますとほぼ平坦で、周辺は切り立ったようになっていて、鳥居の前の石段がなければ前方と左右からは敵が登って来られないようになっています。これは自然の地形ではなく、防御陣地として造成されたもので、岩石城の重要な「曲輪」です。
さらに進んでいくと急な登り坂になり、岩盤に大きな柱穴が2個あります。その間を通って険しい坂を登りますと道の左右に大きな割り石がたくさん置かれています。
さらに登ると平地に出ます。立木を切り払えばかなり広い場所です。ここが本丸だったのでしょう。そこからやや北東に平地が延びています。ここも高い部分を削って、両側は石垣でしっかりと支えています。石垣は平地の端っこに行くとよく見えます。南側の、石垣の一部が少し外れたようになっている所は、下にある井戸におりて行くための石段です。