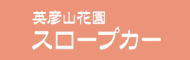ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
添田町の伝説 彦山開山伝説その1
彦山開山伝説(その1)
彦山権現は、もと天竺の摩訶提国にいたが、東方の人びとの幸せをはかるために、どこに行ったらよいのかを知りたいと五本の剣を投げた。そして甲寅の年に中国天台山から海を渡り、豊前国田河郡大津邑に来た。そこを「御船」という。このとき、彦山権現は香春明神に泊めてほしいと宿を頼んだが、狭いことを理由にことわられた。怒った彦山権現は、金剛童子たちに命じて香春岳の木を引き抜かせてしまった。それで香春岳は、岩石が露出して樹木が少ない山肌になってしまった。
その後、権現は彦山にやってきたので、地主神の北山三御前は住むところをゆずり、みずからは中腹に留まっていたが、やがて宗像郡許斐山に移った。敏達天皇丙申歳のことであるという。
彦山権現は、彦山で八角三尺六寸の水晶石を御神体としていたが、般若窟の上に摩訶提国から投げた剣を見つけた。それで、四九窟に御神体を分けて、その守護のために金剛童子たちを置いた。また、彦山三峰には、法体・俗体・女体の三所権現が神の姿であらわれ、人びとの幸せをはかることこのうえなく、その霊験あらたかであった。
その後、彦山権現は、82年後に伊予国石鎚峰に第二剣を見つけて移り、更に6年後、第三剣を淡路国鶴羽峰に、また6年後に第四剣を紀伊国牟漏郡切部山玉那木淵の上に、その61年後に第五剣を熊野新宮南神蔵峰に見つけて移った。更に61年後に新宮東阿須賀社北石淵谷に勧請されて崇拝されていたが、2000年後、甲午歳正月十五日に元のように彦山に帰って来た。
これは、「彦山流記」に記載されているものである。同書は彦山に関する最も古い書籍で、貴重な史料であり、その奥書に「建保元(1213)年癸酉七月八日九州肥前国小城郡牛尾山神宮寺法印権大僧都谷口坊慶舜」とある。