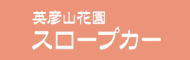本文
国民健康保険税とは
国民健康保険税の税率・税額
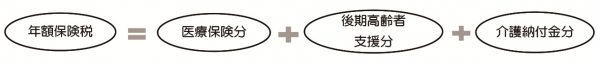
4月から翌年の3月までの1年度分の国民健康保険税額は、「医療保険分」・「後期高齢者支援金分」・「介護納付金分」の合計額です。税額は国保加入者全員分を世帯ごとに算定します。年度途中で国保資格を取得または喪失したときは、加入月数に応じて月割計算をします。
|
区分 |
加入者全員 |
40歳~64歳の加入者 |
|
|---|---|---|---|
|
医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
|
|
所得割 |
7.5% |
2.5% |
2.5% |
|
均等割 |
24,900円 |
10,900円 |
10,400円 |
|
平等割 |
28,300円 |
10,100円 |
8,500円 |
|
限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
各項目の解説
- 所得割 (加入者の前年総所得額-〔基礎控除43万円※所得により制限あり〕)×税率(※一人ずつ計算)
- 均等割 加入者の人数×税額
- 平等割 一世帯あたりの税額
- 限度額 区分ごとに課税される税額の上限額
年度の途中で加入・脱退した時の国保税
年度の途中で加入した場合は、加入月から当該年度の3月までを月割りして計算します。
また、年度途中で脱退した場合は、脱退月の前月分までを月割りで再計算します。
国保税の軽減
世帯の所得額に応じて「均等割」と「平等割」が7割・5割・2割軽減します。
軽減割合は、下表計算式の所得以下の世帯にそれぞれの軽減が適用します。
| 軽減割合 | 軽減対象者の要件(世帯の総所得額) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円 |
| 5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(加入者数×30万5千円) |
| 2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(加入者数×56万円) |
※給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等(国民年金・厚生年金・企業年金など)の支給を受ける人です。
※65歳以上で公的年金収入のある人は、年金所得額から15万円を控除した額で判定します。
※土地や建物などの譲渡所得は特別控除前、農業や営業の事業所得は専従者控除前の金額で判定します。
※加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含みます。
未就学児の均等割額の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
後期高齢者医療に移行した場合の軽減
国民健康保険から後期高齢者へ
これまで国保加入者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことで、同じ世帯の国保加入者が一人だけとなり、引き続き世帯状況に変更がない場合は、国保税の医療保険分と後期高齢者支援金分の「平等割」が最初の5年間は半額、その後3年間は4分の1減額します。
被用者保険から後期高齢者医療へ
これまで被用者保険(職場の健康保険等)の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者であった65歳以上75歳未満の人が新たに国保に加入する場合、申請により、一部国保税が減額します。
非自発的理由で失業した場合
解雇や倒産などにより離職した場合、届出により、離職者の前年所得のうち「給与所得」を30%とみなして軽減の判定、国保税の計算をします。
対象となる人(1、2どちらも該当する人)
- 離職時点で65歳未満の人
- 雇用保険の失業等給付を受ける人で「雇用保険受給資格者」の離職理由コードが11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)23、33、34(特定理由離職者)に該当する人
対象期間
離職日の翌日からその翌年度末まで
届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証(原本)、印鑑、マイナンバーカード
Q&A
Q1) 軽減期間中に就職して社会保険に入ったときはどうなりますか?
A1) 職場の健康保険に加入した場合は軽減措置は終了します。なお、職場の健康保険に加入したときは国保を抜ける手続きが必要です。
Q2) 軽減期間中に就職して社会保険に入りましたが、また失業して国保に加入した場合の軽減措置はどうなりますか?
A2) 再離職などによって国保に再加入したときがまだ軽減期間内であれば、残りの軽減期間に係る国保税が軽減されます。軽減期間の満了後に国保に再加入した場合はこの軽減措置は適用されません。ただし、再離職の際に新たな雇用保険受給資格が発生した場合は軽減期間の再判定がされますので、国保加入手続きの際に新たな雇用保険受給資格者証をご提示ください。
Q3) 軽減期間中に他市町村に転出して、転出先で国保に加入したときは軽減措置は続くのですか?
A3) 転出先の国保においても国保税の軽減措置の対象となります。転出先の市町村で国保に加入する際に、忘れないように手続きを行ってください。
Q4) 以前の住所地で非自発的失業者に該当し、転入して国保に加入する場合はどうなりますか?
A4) 軽減措置の対象となりますが添田町であらためて手続きが必要です。
国保税の納め方
納付方法は、納付書または口座振替にて納付する「普通徴収(7月から翌年2月までの8回)」と、年金からの天引きで納付する「特別徴収(4月から翌年2月までの隔月6回)」があります。
特別徴収の対象となる世帯は、以下の1~3すべてに該当する世帯です。
- 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
※世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収の対象とならないため、納付書か口座振替での納付となります。
※特別徴収の場合でも、滞納がなければ申し出により、口座振替に変更することができます。なお、納付書払いへの変更はできません。
|
仮徴収(4月・6月・8月) |
本徴収(10月・12月・2月) |
|---|---|
|
国保税は前年中の所得などに基づき決定しますが、決定するまでの間、前半3回は前年度の2月分と同額を仮の国保税として納めていただきます |
前年中の所得などに基づき決定した年間国保税から仮徴収額を差し引き、残りの額を後半3回で納めていただきます |
14日以内に必ず届出をお願いします
国民健康保険は、届出日からではなく、他の健康保険の資格がなくなった時点にさかのぼって加入し、国保税もその月分から納めることになります。
また、他の健康保険に加入した場合も、国民健康保険を脱退する届出をしないと、社会保険などの保険料と国保税を二重に支払うことになりますので、早めの届出をお願いします。
申告はお済みですか?
国保税の決定には、18歳以上の加入者全員の所得の申告が必要です。
未申告では軽減判定が適用されず税額が高くなる場合があります。所得がない場合や遺族年金、障害年金などの非課税収入の場合でも、毎年申告をお願いします。